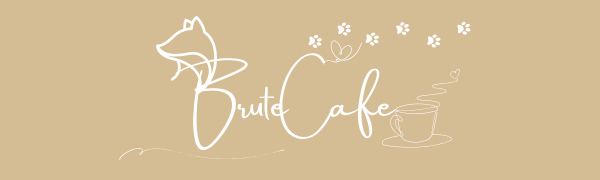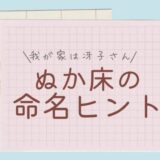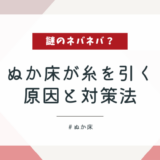調理時間:20分
保存の目安:-
ぬか床を手作りするのはハードルが高いと感じるかもしれませんが、実はシンプルな材料で作り方も簡単です。
我が家では発酵済みぬか床を買ったり、イチから作ったりと色々試した結果、調合済みぬか漬けの素をアレンジするレシピを採用しています。
冷蔵庫保存するのにも丁度よく、初心者も扱いやすい分量になっているので、ぜひ試してみてください!

発酵済みぬか床のおすすめやイチから作るぬか床レシピは別の記事で紹介します
材料(2~3人分の約2kg)
- 伊勢鳥羽志摩特産横丁「ぬか漬けの素」 … 1袋
- 水 … 1L(米ぬかと同量)
- 昆布 … 約15g
- 樽の味「温州みかんの皮」 … 大さじ1
- 新生姜 … 一片(15g)
- きなこ … 大さじ2
- りんご … 1/2個
- 漬ける用の野菜 … 適量
- 酒本舗はな「きぼうのぬか床」 … 1袋 ※足しぬか用
ぬか床を作ろうと思ったら必ず用意したいのは「ぬか、塩、水、昆布、唐辛子」です。
我が家では「ぬか漬けの素」の原材料にプラスして、みかんの皮、新生姜、きなこ、りんご(漬ける用)を必須の調味料として揃えています。
水分量が多く、辛味やクセが少ないので新生姜を使っています。根生姜や土生姜でも問題ありません。
爽やかな香りと防腐効果がある実山椒を含むレシピもありますが、もともと山椒が好きではなく、好みの味にならないので入れていません。
鰹節や煮干し、干し椎茸、柚子の皮も調味料の定番なので、自分自身が好きな食品かどうか、選ぶ際の基準にしてみてください。

動物由来の鰹節や煮干しは腐敗しやすいから注意!
旨味同士がケンカするのを避けるため、2~3種類くらいに抑えるのがベストだと思います。
作り方
① 昆布だしを作る
水重量に対して1%の昆布を目安にして、水1Lに対して約15gの昆布で少し濃いめの出汁を取ります。
昆布の種類に指定はないですが、どの昆布を使うかによって味が変わってきます。
我が家のメインは上品な香りと甘みがあり、澄んだうま味が特徴の「真昆布」。足しぬかのタイミングでは、手に入りやすい「日高昆布」を選ぶこともあります。
市販のぬか漬けの素は昆布が入っているものが多いので、この工程は省略してもOK!作り方②で水1Lをそのまま加えてください。
②「ぬか漬けの素」に調味料と昆布だしを加える
容器に伊勢鳥羽志摩特産横丁「ぬか漬けの素」をザルでふるって入れ、樽の味「温州みかんの皮」 、すり下ろすか小さめに切った新生姜、きなこを加えてよく混ぜます。
昆布だしあるいは水を2~3回に分けて加えながらさらに混ぜます。水の場合は昆布を細く刻むか、かなり小さめの正方形に切って、他の調味料と一緒に足しておくと良いです。粉っぽさが無く味噌くらいになれば良いので、1L使い切らなくても構いません。
しっかりと混ざったら、ぬか床内の空気を押し出すようなイメージで手のひらで表面を平らにします。
③ぬか床に野菜を漬けて発酵させていく
りんごと野菜(特に水分量の多いキャベツ・大根など)を押し込むようにして漬け込み、翌日に取り出してまた新しく漬けます。容器のフチや側面に付いたぬかは、布巾やキッチンペーパーで拭き取ってください。
りんごを漬けることで酵母のはたらきが促進され、マイルドなぬか床になるそう!特有のクセが出にくく、フルーティな香りがしておすすめです。
熟成済みぬか床の中には、りんご酵母を使って発酵させた商品もあります。
伊勢鳥羽志摩特産横丁「ぬか漬けの素」は「捨て漬け必要なし!」をウリにしているので、取り出したぬか漬けは水で洗ってそのまま食べています。乳酸菌が育っていないため、最初はぬか漬けというより浅漬けのような味です。
食べられないくらい塩辛さを感じる時は、同じ野菜を3~4日漬けて取り出す時に野菜の汁をギュッと絞る「捨て漬け」を、3回(約12日間)ほど繰り返します。逆に塩味が足りなくなってしまったら、塩を小さじ2~3程度加えてください。
1日1~2回底から天地を返すようにかき混ぜて新鮮な空気を取り入れ、常温で約2週間発酵させていきます。
④足しぬかしながらぬか床のお世話をする
ぬか床の感触が滑らかになって少し酸味も出てきたら、冷蔵庫に入れてもOKです。
常温管理では1日1~2回、冷蔵庫だと2~3日に1回かき混ぜましょう。冷蔵庫管理をメインにするなら、2週間に1回くらい常温に1〜2日出し、ゆるやかになった乳酸菌の活動を活発にさせてください。
水分量が多いと腐敗するので、我が家では1ヶ月に1回約100gの酒本舗はな「きぼうのぬか床」ときなこ・みかんの皮大さじ1を足して、唐辛子を取り替えるようにしました。このタイミングでりんごを漬け、酵母の力で発酵を促すよう意識しています。
それでも水分量が多く、旨味が足りない時は昆布を追加。水分の多い野菜を漬けた時も、大さじ2~3のぬかを足し、塩も加えて元の硬さになるよう調整しています。
コツ・ポイント
- ぬか床は石鹸で洗った清潔な手で扱いましょう。
- 室温30℃を超える時期の常温管理は過剰発酵の危険があるため、ぬか床づくりに適した季節は春~初夏と秋です。
- 熟成済みのぬか床は発酵を助けてくれるので、手に入る人は作り方②で混ぜ合わせてください。
- アルコール臭が発生しやすい密閉容器(タッパーなど)の場合は、臭いに異変を感じたらフタを少し浮かして様子を見ると良いです。
- 長期間手入れができないなら、少し多めに塩を足して冷蔵庫へ。1週間ほどであれば、捨て漬けをして常温で発酵させれば問題ありません。それ以上の期間になると、フリーザーバッグなどに移し替えて冷凍保存した方が良いです。